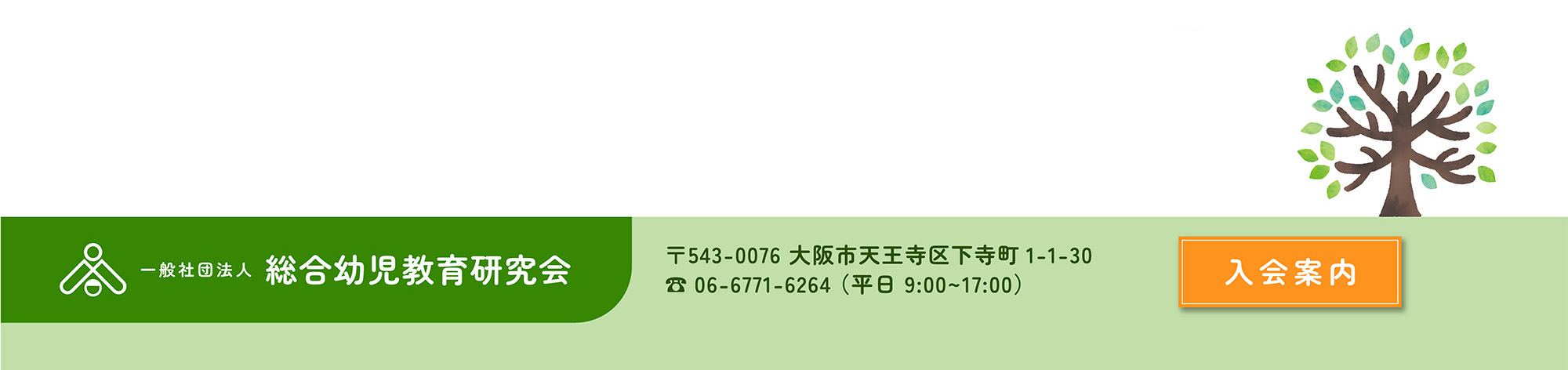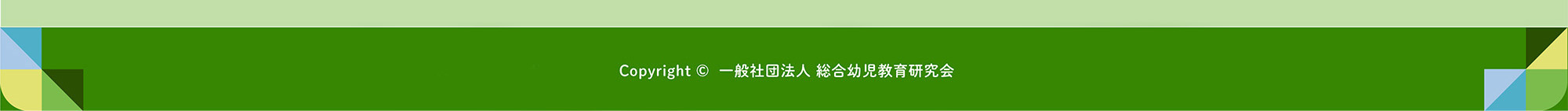『一億三千万人のための「論語」教室』
高橋源一郎著 河出新書刊
『論語』をご存じだろうかと聞けば、多くの人が「もちろん知っている」と答えるに違いない。しかし、実際に全部読んだことがあるかと聞かれれば、おそらく多くの人は首を横にふるだろう。あまりにも有名な古典であるがゆえに、見落とされがちな『論語』であるが、それを作家の高橋源一郎が日本語訳したのが本書である。学術的な正確さではなく、現代に生きる私たちにとっての読みやすさや臨場感を意識した、今風の「超訳」と呼んでもよいだろう。
さて『論語』という書物は、孔子が主宰する私塾での講義を中心に、色々なところで話したことばを採録したものだ。著者が『論語』をはじめて読んだ時、もちろんことばの意味はわかったけれども、結局孔子が何をいいたいのかが、わからなかったそうだ。孔子との対話を深め、それを掴むまで、本書の完成には20年の歳月が費やされた。だから著者にとってこの本は「超訳」ではなく、これ以上に厳密な翻訳はないんじゃないかとまでいう。
パドマ幼稚園では以前から『論語』の素読を行っており、年中児が「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知れば、以って師たるべし」と唱えているのだが、はたして大人でもピンとくるだろうか。本書の訳は軽快であり、こんな風になる。
「昔のことを研究するぐらい誰にだってできるんですよ。大切なのは、そうやって研究したことの中から、いまに役立つ何かを見つけてくることですね。そういう人じゃなくちゃ、先生なんかやっちゃいけませんよ」。
孔子との距離が一気に縮まったが、私たち教師にはなんとも耳が痛いことばである。孔子の思想の中でも最重要なのが「仁」である。「人を愛し、実践すること」などと訳されるが、なかなかむずかしい概念らしく、弟子たちが「仁」とは何かと質問する場面が何度も出てくる。孔子の答えは、たとえばこうである。「つっかえながらしゃべる人がいたら仁者である可能性が高い。つっかえてしまうぐらい真剣に考えるなんて、ほんとうにむずかしいことなんですよ」。
どうだろう。テレビではペラペラとことばを消費する人しか見ないが、私たちの周辺の子どもとのかかわり、同僚とのかかわりにおいても考えさせられる話ではないか。
『論語』を読みなおし、その深さに驚いていると、日本文化の大半は中国から移入したものだという事実に、改めて思いを馳せずにはいられない。日本と中国とは政治的には色々あるが、このような偉大な古典が存在し、かつての日本人もここから人生の多くを学んだことを忘れてはいけないと思う。この内容は子ども以上に、現代の私たちが学ぶべきものだ。
秋田光彦