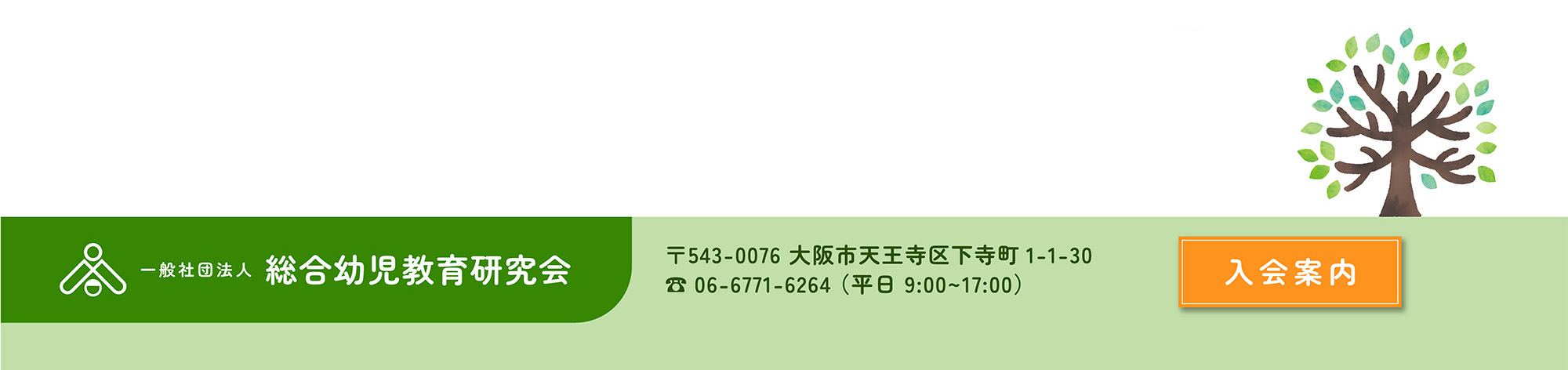5月1日、国立青少年教育振興機構が、親の激励が子の育ちにどう関連するか、興味深いデータを発表しました。
「もっとがんばりなさい」など保護者の子供への叱咤激励は、洗濯物をたたんだり、あいさつできたりといった生活力の向上には必ずしもつながっておらず、親が趣味を一緒に楽しむなどの経験をさせるほど、礼儀やマナー、課題解決力がより身につくという傾向もみられた。担当者は「言葉だけではなく、一緒にやってみるなど具体的な体験を伴うと子供の力は伸びる」としている。(日経新聞5月2日)
調査委対象は小学生中・高学年ですから、一概に幼児期と重ねることはできないのですが、私にとっても至極当然という結果でした。
「叱咤激励」は日本語特有の心情表現かもしれません。「叱咤」は大声で叱ることであり、「激励」は励まし、元気づけること。相反する感情ですが、これを子どもへの「愛のムチ」とかいって正当化する愚を犯してはなりません。
では、「一緒にやってみる」とはどういうことでしょうか。
報道では、「趣味を親と楽しむ」という選択肢しか見当たらなかったのですが、じつは幼少期においては、学びもまた「一緒に楽しむ」がたいせつです。親や教師が知識の権化のようにふるまい、無知な子どもを導くというかたちでは、学びのよろこびも敬いも生まれません。子は親の背中を見て育つといいます。趣味以上に、学習や生活(つまり子どもにとって生きることそのもの)にこそ、大人の共感や共体験が不可欠なのです。
総幼研の教師も、もちろん子どもを励まします。時に「叱咤激励」もあるかもしれません。しかし、その立ち位置は、遠い観客席からではなく、ピッチを子どもとともに走る伴走者としての存在です。
走ることは楽しい。走ることはよろこびだ。そしてそのために努力や協力がたいせつだ。そういった人間が生きることの本質を、教師の心とからだ(もちろん言葉がけもセットですが)を通して共振していかなくてはならないと思います。親もまた同じではないでしょうか。
愛すればこそ、励ます。それは紛れもない人間の美徳ですが、同時に、言葉だけに溺れない、大人と子どもの真の信頼づくりであることをしっかり心得ておきたいと思います。