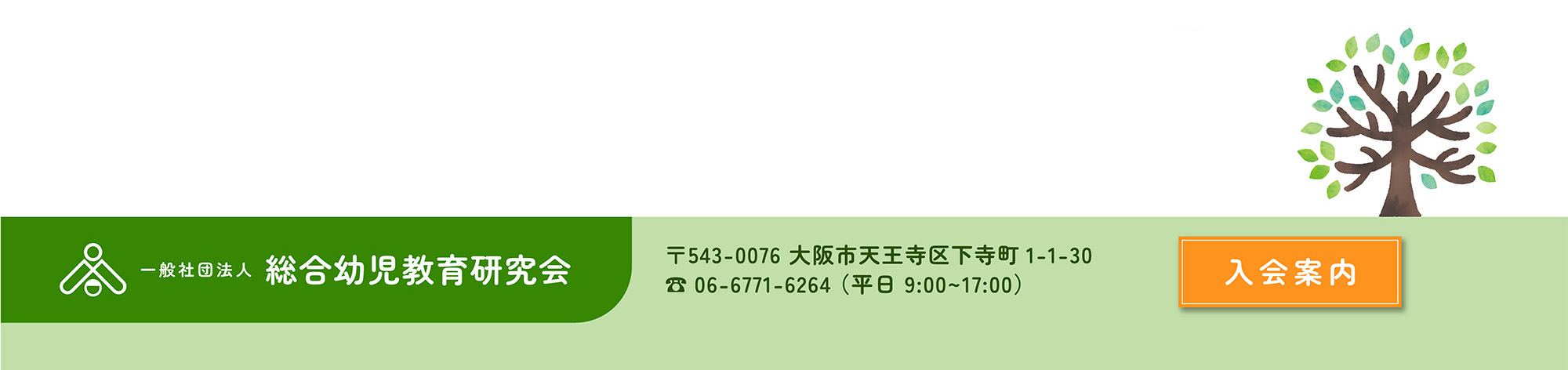あの事件があって以来、テレビではしばしば幼稚園の素読の場面が放映されることとなりました。その映像はかなり強い印象をもって受け止められたのではないでしょうか。すばらしいと思う方もあれば、無理強いされているのではないか、子どもがかわいそうという意見もあるのかもしれません。
パドマ幼稚園でも毎日素読を励行しています。子ども集団が共振しながら唱える形態は、テレビとほぼ変わりはありませんが、読んでいるテキストはまったく違います。あの事件以来、いったい素読で読まれるべきテキストには何がふさわしいのか。幼児にとって素読とはどんな目的を持つのか、改めて考えさせられることとなりました。
素読とは「意味を考えないで、文字だけを声に出して読むこと」です。江戸期以来の幼少教育の主流であり、現代の齋藤孝の音読ブームにつながる、日本の学びの特殊形態といえるかもしれません。
「意味は考えない」のだから、テキストは何でもよいのではありません。
「素読を通じて〈身体化されたテキスト〉は、それ自体で直ちに実用の役に立つような知識ではない。しかしやがて実践的な体験を重ねるうちに、それらはさまざまな場面のうちに新たなリアリティーをもって実感され、よみがえってくる。いわば具体的な実践の場において実感的にテキストの意味が理解され、かつそれが道徳的な実践主体として、人としての生き方のうちに具体化されて示されるようなものである」(辻本雅史「学びの復権」)
「身体化されたテキスト」というのは、可視化あるいは定量化されにくいものです。園児の頃から般若心経を唱えていれば、いずれ仏典を講釈する大人になる、というのでもない。意味がわかるから学ぶ、のではなく、意味を越えたところにある意図を身体に埋め込んでいく。それがやがて真の意味への渇望状態をつくり出す。「子どもの言語状況は、『言葉があまって思いが足りない』というかたちで構造化される」(内田樹)のだと思います。
したがって、テキストは「生き方のうちに具体化」されなくてはならないのですから、自ずと古典的なものが中心になります。たとえれば、敬老の参観で2世代上の祖父母が聞いても、共感できるもの。伝統的な文化財とはそうやって世代を越えて共有されてきたのだろう。意味による合一ではなく、歴史的情景を、ある種の共同幻想(イメージ)としてとらえてきたのだと思います。
そう思うと、素読に取り組む幼稚園は、何をもってテキストとするのか、歴史的に文化的にどう読まれてきたのか、それが子どもの「身体化」にどう影響するのか、そのことにいっそう慎重かつ謙虚でなくてはならないと痛く感じています。