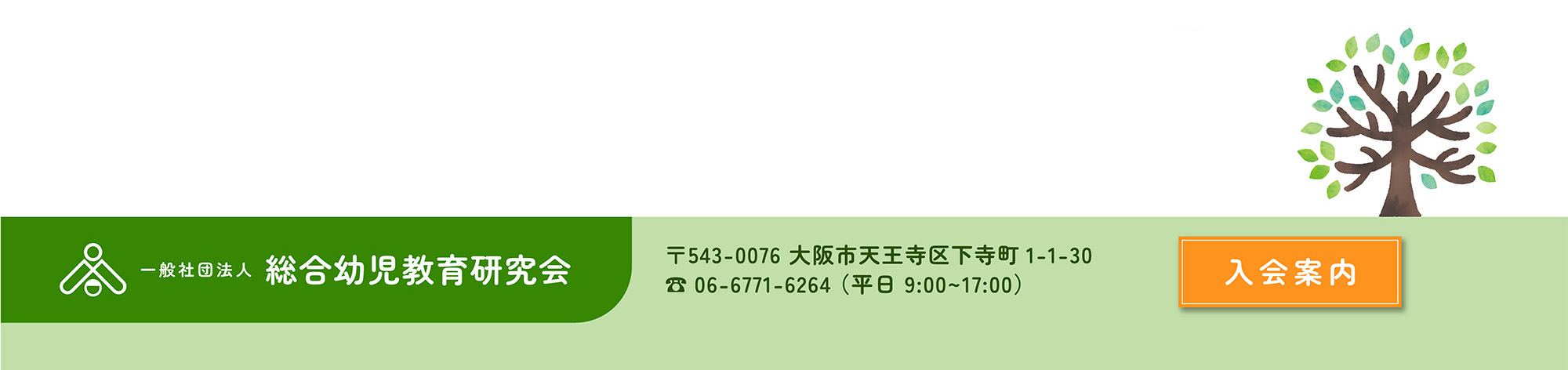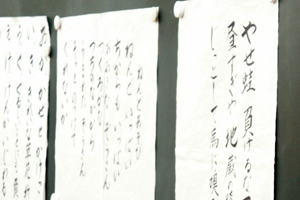
「現代の国語教育では、(その国の)この国語固有の抑揚とリズムの構造を取り出し、洗練させ、身体化し、さらにそれを音楽的なものに昇華してゆくというプロセスが欠落している」と言ったのは、内田樹さんだ(「街場の教育論」)。一部の幼稚園では、ひらがな50音を一音ずつ教えるというが、それは親受けする小学校の準備教育に過ぎないのであって、「身体化」ではない。幼児の間は、意味や解釈など不要であって、けれどゆたかな語感と道理を伝える正しい言葉を届けておかねばならないと思う。
なぜ幼児に…漢字なのか、についてはすでに半世紀ほど前から議論がなされてきた。時代によっては、漢字教育推進者の中にも誤った認識もなかったわけではないが、今はそれを「詰め込みだ」「小学校準備だ」と非難する声は少なくなった。以前は漢字の難度ばかりに目が行っていたが、その教育の実体が漢字を声に出して読むという身体活動にあることが理解されてきたからだ。音読・素読の教育だ。
パドマ幼稚園では、漢字とはすでに半世紀のつきあいがある。さらに30年ほど前から、音読・素読活動が始まり、漢字教育ではなく、漢字を用いながら、知的な身体活動(当園では日課活動というが)へと進化していった。詩歌あり、四字熟語あり、漢文あり…意味など一切説明しない。必要なことは、名句・名文を通して、日本語というテキストを子どもの内部に「身体化」することなのだ。
日本近世の教育思想の研究者、辻本雅史さん(京大名誉教授)の話を聞く機会があった。江戸時代においても一般的だった素読の教育でも、子どもにいきなり「四書」を与え、師匠とともに音読しながら、声の響き、抑揚、リズムで孔子の言葉を身体に埋め込んでいったのだという。むろん中国の古語で書かれた内容について意味など説明もしない、理解もできない。身体化とは自己との同一化をいい、それが思考の型となって、やがて心を育んでいく。「言葉は心の容れもの」であり、そのために教え込む(意味理解)ではなく、滲み込み(習熟)の日本型教育こそふさわしいと指摘された。
私たちは「意味理解」という近代教育の呪縛から逃れられない。漢字を持ちだすと、「意味もわからないのに」とまず意味論を押しつけてくる。理解の過程を踏まえるので、何でも易から難へとカリキュラム化されていく。言葉がいくら入力されても、OSができていなければ、データはこぼれおちていくだけである。それが、子どもたちの言語状況の貧困を招いている。
いかに幼少期に本物の言葉と引き合わせるのか…その機会はいまや幼稚園や小学校にしかない。むろん、そのための教育技法や実際については、十分な検討が必要だが、何もしないまま、相も変わらず「早期教育アレルギー」(という思い込み)がはびこるようであれば、日本の幼児教育は硬直化したままとなるだろう。その隙間を市場主義が横行すれば、「漢字も教えます」という高額な教育商法になりかねない。
総幼研教育でもまったく同じことがいえるのではないか。われわれが何を「教育」というのか、その根拠や目的をきちんと説明していかないと、誤解どころか、子どもの言語状況はますます廃れてしまうことになる。